vol.20
杉本 亜砂子 [大学院生命科学研究科 生命機能科学専攻 発生ダイナミクス分野 教授]
1987年3月 東京大学理学部生物化学科 卒業、1992年3月 東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻博士課程修了、博士(理学)取得。1992年4月-1996年3月 米国ウィスコンシン大学マジソン校 博士研究員、1996年4月-2002年3月 東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻 助手、1997年10月-2000年9月 科学技術振興事業団さきがけ研究21「素過程と連携」研究者(兼任)、2001年2月-2011年3月 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター チームリーダー、2010年4月から現職。
性別による役割期待にとらわれずに、
女性研究者も主導的立場に。
チャンスが巡ってきても「女性だから」と二の足を踏むようなことがあるのであれば、
とても残念、と杉本先生。仕事やキャリアに対する多様な考えを認める一方で、
リーダーシップの発揮をエンカレッジしていく必要があるのではと語ります。

女性であることを意識せずに過ごした女子校と米国ポスドク時代。
女性研究者を増やそうと唱えられ始めて久しいですね。現在、我が国の科学技術分野における女性研究者の割合は大学・研究機関において13パーセントほどに留まっており、政府は科学技術基本計画で3割程度に伸ばしたいとしています。本学の理学部生物学科の女子学生の割合は25%前後、一方、海外の生物学系の大学院では女性が半分、もしくは半数以上を占めるというところもありますから、数的に見劣りする感は否めないですね。私も女性研究者の割合が漸増傾向ではあるものの、期待したほどのスピードでは増えていない、という印象を受けています。結婚・出産・育児などに際しても、好きな研究を続けていきたいという意欲ある女性研究者が増えている反面、チャンスが巡ってきても権限と責任を伴う立場には就きたくないというケースも散見されます。もちろん仕事やキャリアに対する考えの多様性は前提としなければなりませんが――これは個人の資質・能力・志向というよりも、多くの女性が主導的役割を担うためのトレーニングを受けてこなかった、という可能性を排除することはできないでしょう。さらには「女性は男性をサポートする立場」とする“社会的・文化的な性のありよう”が大きく影響しているのかもしれませんね。
私は中高一貫の女子校出身です。男女別学に関する議論は別の機会に譲るとして――生徒会の運営・自治、もっとわかりやすい例を挙げれば文化祭の劇などで、個々人の興味・関心や適性に応じて役割分担や配役を行う環境にいられたのは、とてもよかったと感じています。同様に、性別による固定的な役割期待にとらわれずに過ごせた期間として、博士研究員として米国で働いた4年間があります。非常に居心地が良く、帰国後、再適応するのに一年近く要したほどです(笑)。柔軟で風通しの良い風土も特筆されるもので、例えば共同研究の立ち上げにおいても、セミナーなどで議論を交わし、合意形成されたら、次の日には一緒に研究に取りかかるほどの素早さでした。こうした点は日本の大学も大いに見習うべきなのではないでしょうか。
細胞のうごめきの中に基本原理と法則を見出す。
小学生の頃の愛読書は「キュリー夫人伝」(作者は夫人の次女エーヴ)。工学部出身の父がサイエンス好きで、家には自然科学系の書籍があふれていました。理詰めで考えることが大好きで、紛う事なき“理系”でしたね。中学3年か高校1年生の頃、遺伝学の基礎ともいえるメンデルの法則に触れました。それまで生物学というのはファジーなものという認識があったのですが、物理や数学との親和性が高いことを知り、俄然興味が湧いてきました。生物の先生は、当時はまだ教科書に載っていなかったDNA(1953年ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックが提唱、1962年ノーベル生理学・医学賞受賞)について話してくれ、ワトソン博士が著したその名も『二重らせん』というノンフィクションを紹介してくれたのですが、その本もしっかり我が家の書棚に収蔵されていました(笑)。読み進める内に、当時はまだ萌芽研究分野だった分子生物学を学んでみたいと考えるようになりました。
大学進学後は、脇目もふらず学究生活に入り…といいたいところなのですが、馬術部に所属し、毎日、始発電車で厩舎に直行する日々を過ごしました。やっと2時限目に間に合っても、授業の途中でこっくりと舟を漕いでしまい、クラスメイトにからかわれる始末。でも練習の甲斐あってか、七大戦(全国七大学総合体育大会)の馬術競技、個人の部で準優勝を果たすことができました。
大学院では単細胞生物である酵母の分子遺伝学を研究し、博士号を取得後は、米国に研究の場を求め、C.elegansをモデル生物とした発生遺伝学を探究しました。帰国後の取り組みもその延長線上にあります。研究の醍醐味は、誰も理解していなかったことを世界で初めて解き明かすこと、そして曖昧に思える細胞のうごめきの中に生命発生の基本原理や法則を見出すことに尽きます。顕微鏡の中の細胞は、私たちが理解できていることは、ほんの一握りでしかないことを教えてくれます。私が遺伝子に魅せられてやまないのは、そこに知られざる生命の本質、輝きが秘められているからかもしれません。
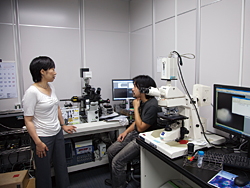
[研究内容紹介]
受精卵から生物個体をつくり出すためには、ゲノムに書き込まれたプログラムに従って、細胞が分裂を繰り返しながら多様な細胞種を生み出すことが必要です。杉本先生の研究室では、ダイナミックな細胞内現象を分子レベルで解析するため、体細胞の総数が959個と少なく実験動物として多くの利点を有する線虫を主なモデル系として解析に取り組んでいます。一方、細胞が分裂する際には「紡錘体」と呼ばれる細胞内装置の働きによって、遺伝情報の担い手である染色体が娘細胞に均等に配分されます。杉本先生(共同研究者:理化学研究所 戸谷美夏研究員)は線虫胚をモデル系とした分子イメージング解析からオーロラAというタンパク質が紡錘体形成に重要な役割を担っていることを見出しました。2011年5月、英科学専門誌を賑わせたこの発見は、新しい癌治療法の開発にもつながると期待されています。
上記インタビュー記事のダウンロードはこちらから