vol.45
中山 啓子 [医学系研究科 附属創生応用医学研究センター がん医学コアセンター 教授/医学系研究科 副研究科長]
1978年 東京都立立川高等学校卒業、1986年 東京医科歯科大学医学部修了・医師免許取得、1991年 東京医科歯科大学大学院医学研究科内科学専攻終了(医学博士)。1991年~1995年 米国ワシントン大学 ポストドクタルフェロー、1995年~1996年 日本ロシュ研究所主任研究員、1996年~1997年 東京医科歯科大学附属病院 医員、1997年~2002年 九州大学生体防御医学研究所 助教授、2003年~ 東北大学大学院医学系研究科 教授。2013年~ 同大医学系研究科副研究科長。1992年 東京医科歯科大学研究奨励賞、2008年 平成19年度医学部・医学系研究科「教育貢献賞」
臨床から基礎研究への転換、複雑精緻な生物を構築する“細胞の神秘”に魅せられて。暗中模索の道を、知的好奇心が切りひらく。
30年ぶりにレッスンを再開したピアノ。「家での練習が不十分なことも、先生はすっかりお見通しなんですね。叱責されるのも新鮮な体験です」と中山先生。教えを乞う立場になってみて、新たに抱く様々な感懐…。「学生さんに接する際の参考にしています」。やさしい視線の先には、後進の存在があります。

よい医師とは――臨床の現場が教えてくれた「人を診る」ことの大切さ。
「私が高校生だった1970年代後半、『女性も働いて自立するのがごく自然なこと』という時代の気運が高まってきていました。男女雇用機会均等法の施行(1986年)までにはまだ間がありましたが、この頃からメディアを通じて働く女性の姿とそのライフスタイルが盛んに紹介され始めたような記憶があります」。事実、日本における女性の就業人口は1970年代の中盤を底にし、増加傾向をたどっていきます。(総務省統計局「労働力調査」)。「私も一生働き続けることに何の疑問も持ちませんでした。ただ当時の女性の多くは、腰掛け的なワークスタイルでしたから、“腰を据えて”働くには資格を持つべきだと考えたのです」。そして医師を目指して進学します。
「6年間はとにかく資格を取るという目標に向けて努力しました。でもそのうちに『よい医師になりたい』と思い始めたのです。どのような医師がよい医師なのか、それはとても難しく、未だに答えを見出せていないのですが、例えば私が知識や技術面で劣ることによって、患者さんの不利益になることがあってはいけないということだけは強く思いました。それは勉強に対する明確な動機付けにもなっていったのです」。しかし、実際の臨床の場に身を置くことによって、「人を診る」ことの重要性が、文字通り肌身で感じられたのだといいます。「担当させていただくからには、最善最良の医療を為すのは当然なのですが、患者さんによっては治療行為よりも手を握って差し上げたほうが喜んでもらえたり、心の安寧につながったりすることがあります。患者さん個々のお気持ちに寄り添うことが何よりも大切なんですね」。
そして30代に入り、思いもよらなかった基礎研究分野へ。「夫の米国留学に同行することになりました。周りの人からは『ご主人をサポートしてあげてね』と言われたのですが、実のところは私も研究をしてみたいと虎視眈々と(笑)。幸いにも受け入れてくれるラボがあり、新しい研究領域への挑戦が始まったのです」。初めて経験することばかり。実際、実験で出した結果も、どのぐらいのレベルにあるのか、全くわからなかったのだと打ち明けます。「暗中模索の日々でしたが、それでも新しいことを学べるのは本当に楽しかったのです」。沸き上がる知的好奇心に導かれて…中山先生が頭角を現すまでに時間はかかりませんでした。
広大・深遠な生命科学の領域から、自身の情熱を注ぎ続けられる研究対象を見つけてほしい。
古今東西の研究者を突き動かしてきたのは、世界で誰も知らないことを先駆けて解き明かしたい、真理を追究したいという知的欲求なのではないでしょうか。「私の場合は、とにかく細胞の神秘に魅せられたのです」と中山先生。「私たち人間を始めとする(多細胞)生物は、さまざまな機能や特徴を持つ無数の細胞から成り立っています。例えばヒトの細胞の数は60兆個ともいわれますが、元はといえば、たったひとつの受精卵から増殖・分化したものです。細胞が正確無比に二つの娘細胞に分かれること、さらに環境に応じて細胞増殖を停止させたり、娘細胞が母細胞と異なる機能を持ったりすることなどは、生物に根源的に備わっている性質でありながら、とても神秘的なことです。そうした私を捉えて離さない“不思議”に向けて、分子生物学の手法でアプローチし、遺伝子という言葉で説明することを目指しています」。研究の延長線上には、1980年代以降、日本人の死因のトップである悪性新生物(がん)の機構の解明も視野に入ってきます。
そして、教え導く立場として、学生さんには広い視野を備えてほしいと語る中山先生。「私たちの研究は成果が伴ってくると本当に楽しいので、ついつい重箱の隅を飽かずに見続けてしまうのです(笑)。でも10年後、20年後にも興味と関心を抱き続けられる、また自分の可能性を賭すにふさわしい研究対象を、広大で深遠な生命科学の領域からぜひ見つけてほしいのです」。加えて、世界を見つめる高い視座を兼ね備えてほしい、とも。「日本の大学の研究室の多くは、ゆるやかなライン組織になっていますが、私が在籍していた米国の研究室は、絶対的権限と責任を持つボス以外は、キャリアにかかわらず一様な存在でした。そうしたフラットな状況から抜きん出るためには、ミーティングなどでも他者とは異なる独創的な発想をアピールする必要がありますし、もちろん目に見える結果も出していかなければなりません。まさに『Publish or perish』(論文を発表せよ、さもなくば消えよ)の世界です。私たちは、そうした苛烈な競争社会にいる研究者たちと伍していかなければならないのです」。学生だから、という甘えは禁物と諭す中山先生。その厳しくも心温かな指導と教育が、一朝一夕には叶えられない成長を促していきます。
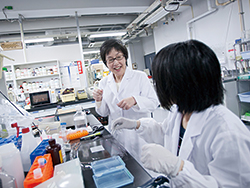
[研究内容紹介]
ヒトの体は、たった一つの受精卵が増殖を繰り返すことによって、多くの細胞からなる一つの個体となります。しかも、それぞれの細胞が同じように増殖するのではなく、それぞれが異なった機能を獲得する、すなわち分化しながら増殖すると考えられています。中山先生は、増殖機構だけではなく、増殖と分化がどのように関連し、どのようにお互いを制御しているかを明らかにするため、遺伝子操作マウスの作製と解析はもちろん、分子生物学・細胞生物学的手法を駆使して、私たちヒトの体の理解という難問に取り組んでいます。このような研究は、細胞増殖制御機構の破たんが原因とされる発がん機構の解明や、分化の一つの形であると考えられる老化を理解することにつながるため、将来的にはそれらの予防や治療へと発展させていくことが期待されています。
上記インタビュー記事のダウンロードはこちらから